震度とマグニチュードの違い|揺れと地震規模の理解
地震のニュースでよく耳にする「震度」と「マグニチュード」。どちらも地震の大きさを表す言葉ですが、指している内容はまったく異なります。
簡単にいうと、震度は「揺れの強さ」、マグニチュードは「地震そのものの規模・エネルギー量」を示します。
この違いを理解しておくと、防災意識を高めることにもつながります。
震度とは?
震度とは、地震が発生した際に人や建物が感じる揺れの強さを示す指標です。
日本では気象庁が定めた「震度階級(0〜7)」で表され、各地の地震計で測定されます。
同じ地震でも、震源地に近い場所は震度が大きく、遠く離れた場所では震度が小さくなります。
震度は、人間の体感や建物の揺れに基づいて決まるため、同じマグニチュードの地震でも場所によって震度は変わります。
たとえば「震度3」は机の上の物が揺れる程度で、多くの人が軽く揺れを感じます。一方「震度6強」では立っていることも困難で、家具の転倒や建物への被害が出ることもあります。
マグニチュードとは?
マグニチュード(M)は、地震そのものが持つエネルギー量を数値化したものです。
アメリカの地震学者リヒターが開発したリヒタースケールが元となっています。
マグニチュードは地震の規模を示す指標であり、震源の深さや広がりに関係なく、地震自体の「大きさ」を表します。
マグニチュードは対数スケールで表され、1増えると地震のエネルギーは約32倍になります。
たとえば、M6.0の地震はM5.0の地震の約32倍のエネルギーを持っています。
このため、ニュースで「マグニチュード7.2の地震」と言われると、非常に大きな地震であることがわかります。
震度とマグニチュードの違いを比較
| 項目 | 震度 | マグニチュード |
|---|---|---|
| 意味 | 地表で感じる揺れの強さ | 地震そのものの規模・エネルギー量 |
| 単位 | 0〜7の階級(気象庁震度階級) | 数字(リヒタースケールやモーメントマグニチュード) |
| 測定対象 | 揺れを感じる場所 | 地震源そのもの |
| 変化 | 場所や建物の構造によって異なる | 地震自体のエネルギーによって一定 |
| 使い方 | 地震被害予測・避難指示の目安 | 地震の規模評価・地震学的分析 |
| 例 | 震度3:軽い揺れ、震度6強:家具転倒の危険 | M5.0:中規模地震、M7.0:大規模地震 |
まとめ
震度とマグニチュードの違いをまとめると、次の通りです。
- 震度:揺れの強さ、場所によって異なる、避難行動の指標
- マグニチュード:地震の規模・エネルギー、地震自体の大きさを示す
災害情報を正しく理解するためには、震度とマグニチュードの違いを把握することが重要です。
震度は「自分のいる場所での揺れ」を、マグニチュードは「地震そのものの大きさ」を表していると覚えておくと、ニュースや防災情報の理解がより正確になります。

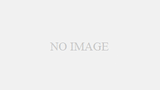
コメント